懺悔の語源はサンスクリット語の懺摩です。これを中国語に訳すと悔過となります。懺摩の懺と悔過の悔をとって合わせると懺悔の出来上がりですね。懺摩でも悔過でも、過ちを悔い改めその許しを請うことに変わりはありません。ところで本来の懺悔はどのようなものだったのでしょう。
原始仏教では、半月毎に教団の反省会が開かれ、比丘達は自分の犯した罪をお釈迦さまや長老に告白してその裁きを受けることになっていました。それが大乗仏教になると、自分の罪を認めて仏前で懺悔文を唱えることによって仏さまに受理され、罪から解放されるという形のものに変わってきたのです。わが天台宗で、盛んに修されている法華懺法という法要があります。まさに懺悔を主とした内容で出来ている法要です。
私たちは意識・無意識にかかわらず多くの罪を負っていますので、こんな時よく懺悔いたしましょう。懺悔によって心を洗い、さっぱりしましょう。一般的に意地がありすぎて「ごめんなさい」の一言が言えない人は、一人ぽっちで淋しい思いをします。「ごめんなさい」と言える勇気を持ちたいものですね。
今年もあとわずか、どうかこの一年を振り返って、心から懺悔をして、新たな気持ちで新しい年をお迎えください。
人が右と言えば左、左と言えば右といい、なにごとも人の言うことに逆らって反対のことばかりしている人です。
そのようなひねくれた態度が本物の天邪鬼にいているからそう呼ばれるのだと思いますが、では本当の天邪鬼とはどんな動物なのでしょうか。天邪鬼とは経典に見られる想像上の動物で、なんでも人の意に逆らうという小鬼です。毘沙門天の足の下に踏みつけられている姿がよく彫られておりますが、人の邪魔ばかりしているので、毘沙門さまにこらしめられているというわけです。
毘沙門さまは多聞天とも言われる仏法の守護神で、四天王の一人として北方の守りをして下さいます。また、七福神の中にも数えられているとおり、私たちに福を与える福の神でいらっしゃいます。もし私たちの心に天邪鬼のようなひねくれた心があったなら、毘沙門さまにこらしめられてしまいますから、心を常に素直にして福を与えていただけるよう精進しましょう。
心はよく鏡にたとえられます。鏡が曲がっていたり、曇っていたりすると、まっすぐなものでも曲がって見えたり、美しいものでも汚れて見えたりしてしまいます。ひねくれて得をすることはまずありません。心をまげることなく、きれいにしていれば自から福がこちらに向かってくるというものです。
来年のお正月には、ぜひ毘沙門さまを念じ、自分の心の中の天邪鬼を追い払って七福神をお招きいたしましょう。
寺院の敷地は広いこととて、江戸時代、名目上は境内となっている部分に町家を建てさせ、寺院の収入をはかることを致しました。この部分を門前地と申します。
また門前町といえば、元々は参道に沿って発達した町のことで、町の人々は参詣人目当てに土産物を売ったり、宿を貸したりして生計を立ててきたわけです。今日、門前町と言えば、善光寺の長野市や、新勝寺の成田市など、寺院を中心に栄えてきた町を指しますね。あるいは、伊勢神宮の伊勢市など鳥居前町も含めて門前町と表現しております。石川県の門前町(総持寺の門前町)のように、地名そのものを門前と名乗っているところもあります。門前は、大小を問わなければ、全国いたるところにある地名と言えましょう。
「門前の小僧」も多いわけです。寺院があれば必ずと言っていいほど門前があります。門前と名乗らないまでも、そんな門前に住んでいれば自然と寺院のことに詳しくなるし、お経も覚えようというものでしょう。
いや、日本人は仏壇というものを家庭内にお迎えしております。この仏壇に向かって毎朝お経を読むおじいちゃん、おばあちゃんの声を聞いていれば、やはり、いつの間にか習わぬ経を読んでしまうでしょう。
日本人には自然に仏さまの教えが伝わり、お経を読む要素が充満しております。将来の日本人のために「理想的な門前」を提供し、習わぬ経を少しでもあり難いもの(良い影響)にしておいてやりたいものです。
仏教では、人に何かを与えるという布施行が四摂法(布施・愛語・利行・同事)の一つになっており、大切な実践行にあげられているのですが、もし貧乏だったらどうしたらよいのでしょう。「人に与えなさい」と言われても何もないではありませんか。でも落胆には及びません。立派に布施行はできます。別に金品に限っているのではありませんから、無財であっても次の七種の布施行なら、たとえ無一物でも、また寝たきりの病人でもできて、しかもいちばん嬉しい布施と言えましょう。すなわち、やさしく見守ってあげる(眼施)、にっこり微笑んであげる(和顔施)、思いやりの言葉をかけてあげる(言辞施)。お手伝いをしてあげる(身施)、幸せを願ってあげる(心施)、席をゆずってあげる(牀座施)、一晩泊めてあげる(房舎施)をいいます。
お世辞とはこの三番目の言辞施がそうなのです。相手を思いやるやさしい言葉、これこそ最も大切な布施行の一つです。まず「おはようございます」の挨拶からはじめましょう。ゴマすりに直結するような歯のうくお世辞ではなく、こころからのお施辞ができれば、お互い気持ちよく暮らせるようになります。言葉は立派な施物になるということです。
寺院の敷地は広いこととて、江戸時代、名目上は境内となっている部分に町家を建てさせ、寺院の収入をはかることを致しました。この部分を門前地と申します。
また門前町といえば、元々は参道に沿って発達した町のことで、町の人々は参詣人目当てに土産物を売ったり、宿を貸したりして生計を立ててきたわけです。今日、門前町と言えば、善光寺の長野市や、新勝寺の成田市など、寺院を中心に栄えてきた町を指しますね。あるいは、伊勢神宮の伊勢市など鳥居前町も含めて門前町と表現しております。石川県の門前町(総持寺の門前町)のように、地名そのものを門前と名乗っているところもあります。門前は、大小を問わなければ、全国いたるところにある地名と言えましょう。
「門前の小僧」も多いわけです。寺院があれば必ずと言っていいほど門前があります。門前と名乗らないまでも、そんな門前に住んでいれば自然と寺院のことに詳しくなるし、お経も覚えようというものでしょう。
いや、日本人は仏壇というものを家庭内にお迎えしております。この仏壇に向かって毎朝お経を読むおじいちゃん、おばあちゃんの声を聞いていれば、やはり、いつの間にか習わぬ経を読んでしまうでしょう。
日本人には自然に仏さまの教えが伝わり、お経を読む要素が充満しております。将来の日本人のために「理想的な門前」を提供し、習わぬ経を少しでもあり難いもの(良い影響)にしておいてやりたいものです。
ある日、母の乳哺に報いようと思い、道眼をもって亡き母の居場所をさがしたところ、お母様はなんと餓鬼道に落ちて骨と皮ばかりになっておられました。目連尊者はこれをいたく悲しみ、自ら母のもとへ行って御飯を差し上げましたが、それが口に入らないうちに火となり、炭と化してしまうばかりです。尊者は号泣して馳せ帰り、お釈迦さまに母を救う方法を尋ねました。お釈迦さまは「吾今まさに汝が為に救済の法を説き、一切の難をして皆憂苦を離れ、罪障を消除せしむべし」とおっしゃって母の救済法を教えてくださいました。これがいまにまで伝わっている盆供養の始まりですが、仏教でいう救済とは単にこの世にとどまらず、あの世にも及ぶ広い意味があるんですね。救護もまた仏の作用をいう言葉であり、「我今まさに十方の諸仏、衆生を救護したもう神呪を説くべし」とあるように、仏さまが私たちを救い護ってくださるという大きな慈悲を表す言葉です。
このように仏さまたちが私たちを救済し救護してくださることにより、世の中が救われてゆくのですから、仏さまは救世者です。救世者とは仏さまの異名で、すべての仏さまがこれに相当しますが、中でも救世観音が一番身近におられるような気がします。世を救い、人々を救済し救護せんとする仏さま見習い、私たちも他の人に対して、縁あらばできる限りの救済・救護活動をしてあげたいものです。
今月は、日夜新型コロナウイルスと戦っておられる、医療従事者の方々に想いを抱き、感謝の気持ちをもってお話させていただきました。
「ただいま」「わあい、お母さんだ」。子供は喜び、安心します。お母さんも子供の顔を見てホッとします。特別な言葉を交わさなくても、母と子は心と心でシッカリ通じ合っているんですね。
この母と子の間柄は、人間だけでなく、すべての生き物にもあります。日本は古来より、母親が子供をいとおしみ、いたわることを「慈しむ」と表現してまいりました。このイツクシムはウツクシムの転で、ウツクシイという言葉を派生させています。今ではウツクシイといえば
 、美の字を当てますが、そういう点で慈と美は一体と言えますね。
、美の字を当てますが、そういう点で慈と美は一体と言えますね。本当に美しい為には、視覚的・聴覚的にウツクシイばかりでなく、母子の間柄のように心がうちとけあうものでなければいけません。
見聞きするものに心を通わせれば、この娑婆が美しい世界となって展開するでしょう。
私たちがそのようにして他人や他の物事に対することを、慈念猶如赤子と申します。「母親が赤ちゃんに対するがごとく、慈しみの心をもって」接すれば、相手は必ずやそれに答えてくれるに違いありません。
共に生き、無償の愛をそそぐ「慈の心」は仏さまの四無量心の一つです。慈・悲・喜・捨の第一番目ですね。仏さまのこの心に習うことにいたしましょう。それにしても私たちの日常の心得はちょっと離れすぎていました。自分の子供にならできることも、隣の悪ガキだったらそうはいきません。自分の子供なら喜べることをコンチクショウと思い、自分の子供なら共に悲しむところをザマアミロと思ってしまいます。願わくは、すべてのものに母子の間柄となり、母のごとく慈愛の心を起こし、子のごとく慈恩に報じ共に生きることのできることを感謝しながら、美しく暮らしてゆきたいものです。
現代人の中には、先祖や子孫にまで考えが及ばす、自分のことだけで精一杯という人もおりますが、いちばん身近な先祖は親であり、一番身近な子孫は子供ですね。親子のつながりを大切にしてこそ、自分も生かされようというものです。
さて、子孫繁栄を願わぬ先祖・即ち子の繁栄を願わぬ親などおりませんが、すべての生物の中で最も子孫繫栄するものは何でしょう。
動物よりも植物であり、その中でも稲が一番ではないでしょうか。一粒万倍という言葉がありますが、これは報恩経の一節からとった言葉で、稲の異名にもなっていますね。春に一粒の籾を蒔けば、芽を出し、分けつして、秋には万倍の実りに増えます。
このことから、ちょっとした善行に対しても多くの善果が得られることを一粒万倍というようになりました。別の角度から考えれば、少しのものでも万倍になるのだから、粗末にしてはいけない、もったいないということにもなりましょう。
お正月の注連縄を稲わらで作るのも、稲の実である米を鏡餅にするのも、稲にあやかって一粒万倍にしてもらいたいと思うからに他なりません。大小の親子餅を重ねた上に、橙を重ね、親子代々繁栄していってほしいと祈るのです。単に行事として神仏にお餅を供えるのではなく、なぜ稲なのか、なぜ重ねるのか等を知っていてほしいものです。
ところで皆様はよくご覧になる方でしょうか。暦を見ると、ところどころに一粒万倍日なる縁起のよい日がありますね。その日に何か善いことをすれば万倍の善果が得られるというのですが、仏教的に言えば、毎日毎日が一粒万倍日です。善行は海山ほども行い、悪行は露塵ほども行わないようにしながら日々を送りましょう。悪行でも万倍の悪果をもたらします。善果を得るか悪果を得るかは自分次第、用心しながら行動して行きたいものです。
真理とは古代インド語サチヤの漢訳で真実の理ということですね。世の中のいろんな現象を事というのに対して、理はその実体とでもいうべきものをさす語ですから、宇宙の究極の実態が真理であるともいえましょう。私たち人間は全く勝手なものの考え方、とらえ方しかできず、見えなければ無いと思ったり、幻想をいだいて無いものをあると思ったり致します。現実にそこにあるものだけをありのままにあると覚ること これが真理に通じる態度ですね。
また、仏教でいう真理は縁起そのものであって、固定した実態ではなく、諸現象をはなれて別にあるわけもないと致します。つまり私たちの生きているこの世界が真理の世界であり、私たち自身が真理そのもののあらわれであるというのです。このように真理は常に私たちと一体ですから、心に覚りを得れば、別に真理を求めなくても真理の方からやってきてくれることにもなりましょう。
ところでもう一つの語・法則とは、この真理認識の規範で、宗教儀式を行う時の決まり、を規則といいました。「こうすればこうなる」「こうしなければならない」という遵守事項ですね。いまでは「一定の条件のもとでいつでも成立する事物相互の関係」を法則と言っていますが、仏教ではいまでもホッソクと読まれて儀礼規範を指すのに使われております。とにかく、私たちは常に真理を求め、法則に従って精進することが大切ですし、これに叶わぬ生き方は必ず破滅することを知っておきたいものです。
植物学的に見たらどうなるかは別として、これをよく説法材料に使っている方もいらっしゃいます。すなわち、「人間も若いうちはトゲを出してイラ立っているが、歳とともに円くならなければいけません。トゲの多いのが生命力のバロメーターにもなるようですが、いつまでもトゲを出していて円くならないのは、自然ではありません」などと。
心コロコロ、 コロコロ心、 トゲを出しては傷がつく
心のトゲは人を傷つけるばかりでなく、反動的に自分も傷だらけになります。

ところで、円満とか円成という言葉ですが、円満とは、お月様が満ちて円くなるように、人の心もまた満ちて円くなることをいいます。さらには、自らも仏となり、衆生もまた仏となることを円満するといい、円満は如来さまの冠詞のようにも使われています。私たちもめいめいが円満な人格をそなえたいものですね。
また円成とはお悟りを完成することで、なにごとかを成就することもまた円成と表現されるようになりました。雲が晴れて、まんまるのお月様が顔を出すと、あたりがパッと明るくなるように、私たちも煩悩の雲を払い、自分のもつ本来のまるい月➡ 仏性を前面に出し、物事を円満に運び、少しでも社会を明るくするなにごとかを円成してゆきたいものです。
一方、活は水が勢いよく流れ出る意であり、解脱(理想)に向かって今日より明日をよりよくしようと精進するさまを指す文字です。この二つが結びついて生活となれば、当然意味もその二つを結び付けたものとなりましょう。単に生きながらえて寿命を全うするだけでなく、理想に向かって生命を向上させてゆく=そんな毎日の暮らし方が、ほかの生物にない人間特有の“生活”という暮らし方にほかなりません。又、人間の生きる道を活路と言いますが、それは仏道の異名でもあります。
 私達はせっかく人間に生まれてきたのですから、人間界からしか行けないというこの活路・仏道を歩み、成仏することに致しましょう。この成仏コースを辿る生活者に、新と再があります。始覚と呼ばれるコースが新で、従因向果、つまり今まで仏に成ったことのない者が修行を積み重ねて成仏するというもの。次に本覚と呼ばれるコースが再で、従果向因、つまり以前に仏であった者が人間界に生まれ、あらためて元の仏界に帰ろうというものです。どちらにしても成仏に向かって精進することに変わりはありませんね。
私達はせっかく人間に生まれてきたのですから、人間界からしか行けないというこの活路・仏道を歩み、成仏することに致しましょう。この成仏コースを辿る生活者に、新と再があります。始覚と呼ばれるコースが新で、従因向果、つまり今まで仏に成ったことのない者が修行を積み重ねて成仏するというもの。次に本覚と呼ばれるコースが再で、従果向因、つまり以前に仏であった者が人間界に生まれ、あらためて元の仏界に帰ろうというものです。どちらにしても成仏に向かって精進することに変わりはありませんね。自分が仏となる存在であることを自覚し、あるいは既に仏であって、人間を救いに人間界にやってきたことを自覚し、人間としての生活、仏としての生活をシッカリやってゆきたいものと念じます。「我も仏」「我は仏」いや「悉有は仏」です。みんなみんな仲良くして共に仏道を歩み、理想的な生活を営むことに致しましょう。
 「どちらへお連れしましょうか」「あなたまかせです」なんていう会話をよく耳にします。何かを決めたり、行ったりする時、自分は何もしないでほかのものにまかせることを、「あなたまかせ」と表現しますね。実はこの言葉、浄土真宗において、信者さんが阿弥陀様の本願にすべてをまかせることをいいました。他力本願と似た意味ともいえましょう。阿弥陀様に自分のすべてをおまかせして、自己のはからいをなくしてしまうことです。
「どちらへお連れしましょうか」「あなたまかせです」なんていう会話をよく耳にします。何かを決めたり、行ったりする時、自分は何もしないでほかのものにまかせることを、「あなたまかせ」と表現しますね。実はこの言葉、浄土真宗において、信者さんが阿弥陀様の本願にすべてをまかせることをいいました。他力本願と似た意味ともいえましょう。阿弥陀様に自分のすべてをおまかせして、自己のはからいをなくしてしまうことです。ところで皆さんは彼岸という語をご存じですね。彼岸とは仏さまの居られるあちら側の世界です。これに対して此岸といえば、煩悩にさいなまれている私たちのこちら側の世界を指します。彼岸と言わずに彼方、此岸と言わずに此方と言っても同じです。今では彼方此方はあっちこっちということですが、仏さまの悟りの世界が、彼方、私たちの迷いの世界が此方なんですね。そして彼方に居られる仏さまがあなたであり、中でも人気の高い阿弥陀さまが代表してあなたとなったようです。あなたとは阿弥陀さまの別称だったということですね。
私たちがいま使っている「あなた」は二人称ではきみの尊敬語。三人称ではあの人の尊敬語になっていますが、自分以外の
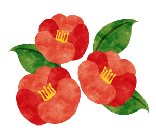 人を阿弥陀さまと同格あつかい、敬って「あなた」と呼ぶのは、悪いことではないでしょう。
人を阿弥陀さまと同格あつかい、敬って「あなた」と呼ぶのは、悪いことではないでしょう。自分の相手方を尊び敬うのはよいですが、「あなたまかせ」がサボル行為の逃げ口上にならないよう、くれぐれも心したいものです。本来の「あなたまかせ」は、自己のはからいをうちすてて、「一切を阿弥陀さまにおあづけすることですから、すごく難しく厳しいものだということを知っておきたいものです。本当のあなたまかせができる人は、妙好人であり、生き仏であると言っても過言ではないでしょう。