業とは、人間が為す行為のことです。すなわち、体での動作、口での言葉、心に思う考えの三つをさし、これらを身口意の三業と言います。この身口意の三業は因果関係とつながっていて、無限の過去から無限の未来へと伸びています。そして悪い業が原因となれば悪い結果、善い業が原因となれば善い結果がその報いとなり、輪廻してゆくわけです。
 経典によると、私たちがその報いを受ける時期には三つあり、すぐ受ける場合、しばらくして受ける場合、忘れた頃受ける場合とがあります。酒を飲むとすぐ赤くなり、飲酒運転で免停なんていうのは第一の例でしょう。また、歯を磨かないでいて虫歯になったり、若い頃の不節制が年老いてからたたったりするのは、第二、第三の例でしょう。この世でやったことの報いはこの世で受ける。この世で受けなければあの世で受ける。あの世で受けなければ、さらに次の世で受けるという風に、引き伸ばして考えることもできます。とにかくいずれは、善業、悪業の報いを受けなければならないのですから、前後を考えないでバカなことをしでかして、「うまくいった」などと、得々としていると後で毒を取られることになります。この世で好き勝手わがままに生きていては、あの世でとられる毒は、どんなにひどいでしょう。
経典によると、私たちがその報いを受ける時期には三つあり、すぐ受ける場合、しばらくして受ける場合、忘れた頃受ける場合とがあります。酒を飲むとすぐ赤くなり、飲酒運転で免停なんていうのは第一の例でしょう。また、歯を磨かないでいて虫歯になったり、若い頃の不節制が年老いてからたたったりするのは、第二、第三の例でしょう。この世でやったことの報いはこの世で受ける。この世で受けなければあの世で受ける。あの世で受けなければ、さらに次の世で受けるという風に、引き伸ばして考えることもできます。とにかくいずれは、善業、悪業の報いを受けなければならないのですから、前後を考えないでバカなことをしでかして、「うまくいった」などと、得々としていると後で毒を取られることになります。この世で好き勝手わがままに生きていては、あの世でとられる毒は、どんなにひどいでしょう。善い報いを受けるためには、こうして元気に生きているうちに、ぜひ良いことを積み重ねておきましょう。そう、積立貯金は、後で受ける程たくさんのお金となっています。
 たがない。これが因縁というものだ。」と解釈した人がおりました。
たがない。これが因縁というものだ。」と解釈した人がおりました。 御手洗が今や例の場所をさすこととなり、しかもそれが常識的なのは残念ですが、少なくとも私たちはこの語が本来さすものを知っておきましょう。そして手を洗うことによって心をも同時に洗い清め、敬虔な気持ちで神仏と対面することを心掛けたいものです。
御手洗が今や例の場所をさすこととなり、しかもそれが常識的なのは残念ですが、少なくとも私たちはこの語が本来さすものを知っておきましょう。そして手を洗うことによって心をも同時に洗い清め、敬虔な気持ちで神仏と対面することを心掛けたいものです。 また、海のタコを取るときは、蛸壷を沈めて待ちます。タコが入ったころを見計らって壷を上げればよいのです。タコは逃げれば逃げられるのに、居心地のよい壷に執着して、引き上げられてしまうというわけです。
また、海のタコを取るときは、蛸壷を沈めて待ちます。タコが入ったころを見計らって壷を上げればよいのです。タコは逃げれば逃げられるのに、居心地のよい壷に執着して、引き上げられてしまうというわけです。 よく「これも何かの縁でしょう」とか「あれは縁なき衆生だ」とか言いますよね。くされ縁、縁故就職、内縁関係などもよく聞く言葉です。このように日常よく使われている縁ですが、これは仏教思想を一言で表現したものといっても過言ではないでしょう。仏教の考え方に「物事はすべてめぐりあわせによってそのようになっている」というのがあります。つまり何かが「そうなっている」のはすべてそうなる原因があったためであり、その原因を助成する事情とか条件のはたらきという「縁」が作用してそうなったのだと考えるのです。たとえば春蒔く種は原因であり、太陽や水や人の手入れ等が縁、秋の実りが結果です。これを因果と言っていますね。また、人と人との出会いの場合、私とあなたという二つの因が不思議な縁のはたらきによって出会うのですから、合縁機縁(愛縁奇縁)といいます。
よく「これも何かの縁でしょう」とか「あれは縁なき衆生だ」とか言いますよね。くされ縁、縁故就職、内縁関係などもよく聞く言葉です。このように日常よく使われている縁ですが、これは仏教思想を一言で表現したものといっても過言ではないでしょう。仏教の考え方に「物事はすべてめぐりあわせによってそのようになっている」というのがあります。つまり何かが「そうなっている」のはすべてそうなる原因があったためであり、その原因を助成する事情とか条件のはたらきという「縁」が作用してそうなったのだと考えるのです。たとえば春蒔く種は原因であり、太陽や水や人の手入れ等が縁、秋の実りが結果です。これを因果と言っていますね。また、人と人との出会いの場合、私とあなたという二つの因が不思議な縁のはたらきによって出会うのですから、合縁機縁(愛縁奇縁)といいます。 仏様が医者に喩えられるものとして、法華経にはこんなお話が載っております。
仏様が医者に喩えられるものとして、法華経にはこんなお話が載っております。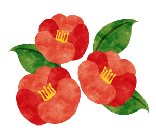 、人の身を受けて生まれるということは、実はほとんど確立のない大変まれなことだと分かります。これを「人身受けがたし」と表現していますが、人身を受けた上に仏さまの教えに出合うとなるともう本当に大変な事です。
、人の身を受けて生まれるということは、実はほとんど確立のない大変まれなことだと分かります。これを「人身受けがたし」と表現していますが、人身を受けた上に仏さまの教えに出合うとなるともう本当に大変な事です。