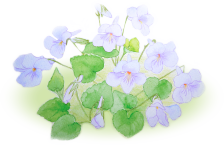 仏教では単に仏祖への報恩行を説くばかりでなく、四種の恩をあげ、四恩の総てに報ずることはもちろん、生きとし生けるものを資けることを説きます。
仏教では単に仏祖への報恩行を説くばかりでなく、四種の恩をあげ、四恩の総てに報ずることはもちろん、生きとし生けるものを資けることを説きます。四恩のあげ方は経典によって多少異なりますが、一般には大乗本生心地観経の ①父母恩 ②衆生恩 ③国王恩 ④三宝恩を採っております。まず父母恩ですが、自分を養育してもらった父母の恩ですね。
この父母恩は、四恩をどんな風に数えようとも必ず入っている恩ですから、それだけ大切で忘れることのできない恩と申せましょう。又、報恩田(略して恩田)という言葉がありますが、報恩田とは養育・教育をしてもらった者、即ち恩返しの対象で、父母のほか師長(先生や年長者)も入ってまいります。
第二の衆生恩ですが、共に生きている皆様全部の恩ということですね。人は支え合って生きています。知らない人からも、いや地球上のすべてに支えられて生きています。だから私たちは生きとし生けるものに恩返しが必要なのです。
第三の国王恩というには、為政者からの恩ということですね。国が平和であればこそ、私たちは幸福に暮らせます。戦争が無く、国が豊かになっているのは、為政者に恵まれていればこそでしょう。第四の三宝恩はもちろん仏法僧の恩ですね。素晴らしい教えとそれを説き伝えてきてくれた方々の恩に報ずることは何よりも大切です。 今の日本には忘恩の徒がやたら増えました。感謝どころか不満だらけで「この不満を誰にぶつけてやるか」と真剣に悩む者さえ出ている有様です。お互い感謝しあう暮らし易い世にもどしたいものですね。