「軽く会釈する」「会釈を交わす」・・・「会釈」という語を現代の我々は、軽いあいさつと受けとめています。ですからその形態も、すれ違いざまにニッコリ笑ったり、片手を上げたり、小さく礼をするといったささいな行為になるのが一般的だ。しかし、そのような何気ない、あまり重要とは思えない日常行為を表す文字としては、会釈はいささかかたい感じがいなめません。
実はこの語は、仏教の中ではもっともむずかしいニュアンスがこめられていたのです。この語は「利会通釈」を略したものとされています。つまりは、互いに矛盾するように見える説を照合して、その間に、合い通じる意味を見いだして融和させることで、これまた、「会通」とも呼ばれました。事情を理解する、合点する、といったぐあいに俗っぽく解釈することもできるでしょう。
それがやがて相手の気持ちを考慮し、心配するという意味になり、思いやり、愛敬へとつながり、現在の我々が使っている、軽いしぐさへとなるわけです。
しかし現代人が交わす会釈は、相手を理解するというより、敵意がないから安心ですよ、といういささかごまかしめいたニュアンスがこめられている、と考えられはしないでしょうか。本当の会釈とは、あいまいな妥協ではなく、真の対立から生まれるものかも知れません。
|
| 合 掌 |
| 平成29年 12月1日 |
|
『瓜子姫とあまのじゃく』などの民間説話にしばしば登場し、最後には決まってやっつけられてしまうのが、この「天邪鬼」。他人の心の中を探るのが上手で、物まねをしたり口まねをしたりするが、必ずと言っていいほど逆らうのが、この鬼の癖です。そのために現在でも、人と異なる意見の持ち主、大勢に妥協しようとしない変わり者を天邪鬼と排除したりします。一説には、巫女(みこ)の天探女(あまのさぐめ)から生まれたともいわれています。
ところで仏教ではこの天邪鬼、仁王様や四天王にいつも踏みつけられている状態で登場します。ところが当初は毘沙門天(びしゃもんてん)のおなかにある鬼面の名が、俗に「海若(あまのじゃく)」と呼ばれていたとか。これはもう、いたずら小僧、憎まれ小僧どころか立派な水神でした。それがどうして足の下に踏みつけられるようになったのかは、よくわかっていません。
この天邪鬼、仏教ではひねくれ者というニュアンスより、どこか愛敬のあるひねくれ者という存在で扱われているケースが多いようです。そのために、姿かたちも憎めない小鬼となったのではないでしょうか。同じ鬼でも、子供の鬼のいたずらは、許すしか方法がないのです。そんな意味では、仁王様に踏みつぶされている天邪鬼は、罪をこうむっているというより、軽いおしおきをこうむっていると解釈したほうがいいのかも知れません。
|
| 合 掌 |
| 平成29年 11月1日 |
|
内弁慶、弁慶の泣きどころ、弁慶の立ち往生などと日常会話によく出てくる弁慶って、どんな人だったのでしょう。
平安時代の末期に熊野別当の子供として生まれ、幼名を鬼若丸と申しましたが、長じてのち坊さんとなり、武蔵坊と名乗りました。天台宗比叡山西塔に住む豪遊無双の怪僧として知られたそうです。彼の豪勇ぶりは右に出るものがなく、数々の英雄伝説が作られましたが、その一つがあの有名な、京都五条大橋の話でありましょう。彼は五条大橋で牛若丸と戦って負けると、すぐ牛若丸つまり義経の家来となり、その後ずっと義経に従って、武勇をあげ続けることになります。
義経が兄、頼朝に追われる身となってから、共に逃げる話も有名でしょう。安宅の関(石川県小松)で義経主従が、関守・富樫左衛門に見とがめられた時、弁慶の機転と左衛門の情によ って無事関所を通りぬける「勧進帳」の話は歌舞伎十八番の一つになっていますね。また奥州平泉(岩手県)における衣川の合戦で、義経を守ろうとして持仏堂の前で立ちはだかり、薙刀を杖にしたまま、体中に矢を受けて立ち往生した話も有名です。このことから進退きわまったことを弁慶の立ち往生というようになりました。 って無事関所を通りぬける「勧進帳」の話は歌舞伎十八番の一つになっていますね。また奥州平泉(岩手県)における衣川の合戦で、義経を守ろうとして持仏堂の前で立ちはだかり、薙刀を杖にしたまま、体中に矢を受けて立ち往生した話も有名です。このことから進退きわまったことを弁慶の立ち往生というようになりました。
更に弁慶が大変強かったことから、強いものの代名詞としても弁慶が使われるようになりましたね。力強く走る機関車に「弁慶号」というのがあったのを思い出します。
そんな弁慶と言えども弱い部分はあったに違いありません。急所、特に向う脛のことや、威勢を誇る者の弱点を「弁慶の泣きどころ」と言いますから・・・。
また、外では弱いが、内方にだけは強いものを内弁慶というのも、おもしろいと思いませんか。
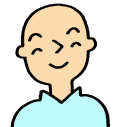
いろんな場面に登場する弁慶さん、僧侶としてよりも僧兵姿で親しまれている弁慶さんの強さと潔さに学んでゆきたいと念じている次第です。
|
| 合 掌 |
| 平成29年 10月1日 |
|
お釈迦さまが城を出て森に入って剃髪した際、王子さまとして身に着けていた立派な衣服を、猟師の粗末な服と交換したという伝説が残っています。つまりは、汚れた服です。この汚れたという形容詞が梵語でカーシャーヤと言い、これには赤、赤褐色、暗示色つまり汚い雑食という意味もありました。これが後に、僧侶が身に着ける衣服「袈裟」を表す言葉となるのです。
お釈迦さまを慕う出家修行者たちは、そうした質素の精神を尊び、死人を包んで墓所に捨てたボロ布などを拾ってきて洗濯し、継ぎ合せて用いたというからすごいですね。現在の袈裟も、方形の布を縫い合わせて作られていますが、これはボロ布を継ぎ合わせた名残なのです。
ところがこの質素な衣服も、自然環境の異なる中国、日本に仏教が伝わるにつれ、大きく変わってきました。インドと異なり、寒さも厳しい中国、日本では下衣を用いるようになり(衣)、その上に着て肩から掛けるのが袈裟と呼ばれるようになりました。それがやがて、修行用の衣服から儀式用の衣服になり、現在のように豪華なものへと変わっていくのです。
東南アジアの諸国では、今でも黄色みを帯びた褐色の衣服を左肩から右脇下にかけて着用していますが、あれこそが本来の袈裟なのです。しかし、お釈迦さまの精神はしだいに忘れられ、袈裟は仰々しくなり、「大袈裟」の言葉が生まれてきたのです。現代の日本の僧侶たちの、あの金ぴかの袈裟をみて、お釈迦さまはどんな感想をもらすでしょう。
袈裟の、一方の肩から斜めにかけて着る様子を表す言葉が「袈裟懸け」、と言いそこから「袈裟斬り」の表現が生まれました。
|
| 合 掌 |
| 平成29年 8月1日 |
| 主婦と生活社「仏教のことば 早わかり事典」ひろさちや監修 より |
|
中国の宋代に生れた隠語で、皆さんもよくご存じのお酒のことです。インドでは古来からお酒をたしなまないことが美徳とされ、戒律でも、飲酒は「顔色が悪くなり、人相が変わる」果ては「死後は悪道に堕ちる」とまで言われました。
しかし仏教が中国へ伝わると、様相は一変します。中国のお寺は、主として山岳地帯に建てられました。そんな地域では、冬ともなるとシンシンと冷え込みます。だから、お酒で暖でもとらねば耐えられなかったのでしょう。
そこで中国のお坊さんたちは、このお酒を智恵の水「智水」であると決めるのです。お酒はときには気違い水にもなりますが、智恵の水にもなる。彼らは勝手に都合のいい方を選んだのでした。そしてつけたのが「般若湯」というわけです。
「般若」とは、梵語で智恵のことです。それも、悟りを得た最高の智恵のことです。つまり、お酒は智恵を生む水であると考えを改めることにより、初めて中国のお坊さんたちは後ろめたさを消し去ったというわけです。
ちなみに能面の一つに、嫉妬や怒りなどをたたえた般若面というものがありますが、これは般若湯を飲みすぎた訳でもなく、智恵が曇った際の顔でもなく、あくまでも鬼女です。面打ちの般若坊が創造した型なので、この名前がついたのでしょう。
|
| 合 掌 |
| 平成29年 7月1日 |
|
味の最上級の形容、さらには物や行為の極まりを表す言葉として、我々はしばしばこの言葉を使います。
もともとは仏典に登場する「五味」が起源となります。つまり、乳味・酪味・生酥味・熟酥味・醍醐味。これら、牛乳を精製していくとしだいに生まれる五つの味なのです。その最上のものが醍醐というわけです。
それでは、実際はどんな食べ物だったのでしょう。現在のバター、あるいはチーズという説もありますが、はっきりしません。
『大般涅槃経』というお経には、「醍醐は最上にして、もし服する者あれば、衆病みな除く」とあります。つまりは薬効もあったわけで、たっぷりの乳酸菌を含んだ甘くてトロリとしたもの、であったことは確からしいです。
さらには、この五味を修行者や一般大衆の素質、能力の深さ浅さの程度を表す言葉としても用いられました。また、お釈迦様の説法の仕方が、五味のように次第にレベルが高くなっていったというたとえに用いられ、醍醐は仏様の最上の教えをも指しています。
ちなみに五味と並んで「八珍」という味の表現もあります。牛・羊・トナカイ・鹿・くじか(小型の鹿の一種)・猪・犬・狼。これらが転じて、珍味をそろえた食膳を表す言葉となったのです。
|
| 合 掌 |
| 平成29年 6月1日 |
|
どこででも見かける平凡な出来事、ありさま、と現代の我々の言葉をそれこそ日常茶飯に用いていますが、本来はもっと大切に使いたい言葉です。
禅家では、あり合わせのものを「家常(かじょう)」と呼びました。つまりは、家の中にいつもあるもの、家の常。当然、誰の目にもありふれた、なんでもないもの、どうでもいい習慣にしか映らない。そこでまず「家常茶飯事」という言葉が生まれました。そして、一般的に用いられるようになり「家常」が「日常」にかわり「日常茶飯」になったわけです。
 つまりは、人間、毎日の常としてお茶やご飯を食べます。そして、それを何も特別なこととは思いません。同じように、高邁(こうまい)な真理も、平凡な毎日の暮らしの中で、それこそ、ありふれた行為のごとく実践されてこそ意味がある。というのがこの言葉の本来の真意です。逆に、真理なんてたかがこんなものにしかすぎないのさ、という皮肉なニュアンスも込められているかもしれません。「日常茶飯事」も同じ意味です。 つまりは、人間、毎日の常としてお茶やご飯を食べます。そして、それを何も特別なこととは思いません。同じように、高邁(こうまい)な真理も、平凡な毎日の暮らしの中で、それこそ、ありふれた行為のごとく実践されてこそ意味がある。というのがこの言葉の本来の真意です。逆に、真理なんてたかがこんなものにしかすぎないのさ、という皮肉なニュアンスも込められているかもしれません。「日常茶飯事」も同じ意味です。
しかし、お茶を飲んだり、ご飯を食べる習慣は無意識に身に付きますが、真理がごく平凡は日常生活の中に存在することを認識するまでには、そうとう時間がかかると思います。
|
| 合 掌 |
| 平成29年 5月1日 |
| 主婦と生活社発行 「仏教のことば 早わかり辞典」より |
|
ヒニクは当てこすりの意味です。日本では、起き上がりこぶしで有名な達磨大師に由来する言葉です。達磨大師は弟子たちの見解に対して、思考が足りないときは、皮や肉のように薄っぺらだと辛辣に批判しました。また、優れた意見の時には骨を得たとか骨髄に達するものだ、と褒めたのです。皮肉は骨髄に達していないということです。
達磨大師は南インドの生まれで、禅を中国に伝えて中国禅宗の祖と呼ばれています。中国では、梁の武帝に会ったときの話が有名です。仏教に深く帰依していた武帝は「わしは多くの寺を建て、坊さんに布施してきたがどんな功徳があるのだろうか」と問います。大師はにべもなく「(何かの為にした布施には)功徳なんかない」と突っぱねます。たとえば、ケーキを友達と分けるとき、いま分けておけば後でお返しがもらえる/食べられずにかわいそうだから/余ってるから/二人で食べたほうが楽しい・・・の内、どれが一番美味しいかを考えていただければ、布施の心が分かっていただけるでしょう。いまの日本だと「もうおやつの時間よ、帰ったら」と友達を帰してから、自分の子だけにケーキを与える親が、当たり前?
有名な達磨大師を外護しようと思っていた武帝はさらに「仏教において一番聖なるものは何か」と問います。これにも「そんな特別なものはない」と『おれがという我』にこだわっている武帝をたしなめます。すると「前にいるおまえは聖人ではではないのか」とまだ名声にこだわります。大師は「しらん」と最後まで噛み合わず、武帝の怒りに触れた大師は、梁を逃れて嵩山少林寺にこもりました。
ここにも、現代の日本人が失ってしまった矜持があります。武帝にへつらって信任を得た方が、布教のためにはよいでしょう。しかし、それでは本物が伝わらないと大師は思ったのです。仏教においては、水を増やして大勢に分け与えるより、まず一杯の水をこぼさずに伝えることを優先するのです。少林寺にこもった大師は、壁に向かって9年間も座禅をし続けました。その不撓不屈の姿を写し取ったのがダルマさん人形です。そして、慧可という待望の弟子ができました。左手の肘を切って差し出し、不退転の覚悟を示して入門を許されたという、すさまじい逸話を残しています。ここに、一大思想を形成する禅宗の礎が固まったのです。
|
| 合 掌 |
| 平成29年 4月1日 |
|
ご存知の通り、荼毘は火葬のことです。
人を葬る方法はさまざまですが、葬儀の目的は、腐っていく遺体の処理と死んだ人の記憶の処理にあります。火で焼く、土に埋める、鳥獣に与える、海や川に流したり、野山にさらす、ごく稀に食べることもありました。火で焼けば、煙となった故人の魂が天に戻ると思いました。毎年緑の生命を生み出す大地に埋めると、芽吹いて再生します。鳥に捧げれば、大空に舞い上がり、獣が食べれば命が巡ります。海や川に流したり野山にさらせば自然の循環の中に戻って浄化されます。
インド人の想いは、白い屏風のように浮かぶヒマラヤの雪の峰 神々の座に帰ることです。そのヒマラヤから流れ出る水で身をすすぎ、ついにはその川に骨を流します。川は流れ下って海に至り、龍の起こした竜巻によって天空へと戻っていき、清らかな雪となってヒマラヤに降ります。その故に、ヒンドゥー教の人々は死期が近づくと、聖地ベナレスを目指します。沐浴場のすぐ上手に火葬場があり、ここで焼かれた遺体はすぐさまガンガーに流され、理想の終焉を演出するのです。
お釈迦様は自分の死期を悟られると、最後の旅を生まれ故郷へと取られました。何不自由なく育ったカピラバスドウ、城の門を出るたびに感じた生老病死の無常の苦しみ、愛馬とともに城を捨てた45年前が頭をよぎられてことでしょう。もし、無事にカピラの町に着かれたら、次の歩みはと考えたとき、それは北に連なる神々の座しかありません。残念ながら、歩みはクシナガラの沙羅(さら)の林で止まりました。北枕は病臥するお釈迦様の姿で、頭を北に向けて涼しく、足を南に向けて暖かくという頭寒足熱、そして半身で西を向くと心臓が圧迫されない楽な寝方でした。そのままの姿で亡くなられたので、北枕は死の代名詞となってしまい、不吉だと嫌われています。
お位牌を安置する四華台は、お釈迦様の寝床の陰をつくった沙羅の木です。悲しみのあまりに枯れてしまったので白い紙で作ります。一週間後、迦葉尊者の帰りを待って火葬され、その遺骨を巡って危うく戦争が起こりかけたと仏伝は伝えています。
|
| 合 掌 |
| 平成29年 3月1日 |
|
矢鱈は当て字です。正式には八多羅と書き、雅楽の八多羅拍子からきています。とても早いリズムでしから、よほどうまくないと合いません。演奏がムチャクチャになってしまいます。また、ヤターラは梵語でとてもテンポの早い踊りです。ここにも「むやみに」とか「たいへん」という意味が込められています。
さて、キリスト教には讃美歌もあり聖歌隊まであります。最近ではゴスペルミュージックまであってにぎやかですが、仏教ではお経は音痴の代表みたいだといわれます。ところが仏典では音楽はあらゆる場面で欠かせません。まず、4月8日のお釈迦様誕生のときは、妙ネルなる音楽が天井から流れ、甘い雨(甘露)がふり、天女は花吹雪を散らします。この音楽を奏でるのは、敦煌の壁画で有名な技芸天です。さらにわが国で絶大な人気を博した音楽と豊穣の女神、弁天さま(弁財天)はサラスバティーという河の名に因んだ天女で、琵琶を抱いて優美です。
ところで、河の名前がなぜ音楽の神の名前になったのでしょう。
昔から、林に住んで修行した出家たちにとって自然の音は神の声でした。また、禅者は自然の声で悟りを開きました。比叡山でお堂に籠って座禅をしたり、念仏を唱え続ける修行をした方々に聞きますと、鳥のさえずり、風が木の枝を渡る音などが、心地よく聞こえ、季節の移り変わりを感じさせてくれる、と申します。『観音経』にも「梵音海潮音」と出てきます。梵音とは仏様の声で、この世のものとは思えないほどの美声であるといいます。寺にあって毎日梵音を響かせるのも、それは大梵鐘です。大晦日に毎年放映される百八声の除夜の鐘です。鐘の音は、それを聞くだけで悟りを得るといいます。同時に、波の音も、谷川の音も、仏様の声をいや仏様の命を伝えているのです。
その音の仏様が観世音菩薩です。人々の苦しみを聞き、声にならぬ苦悩を観てとり、ただちにその人が望む姿に身を代えて救ってくださいます。それで三十三とも、百ともいわれる変化の姿をおもちです。さらに、多様な願いを叶えてくださる夢が、千手の観音様を造形しました。中国、日本でもっとも信仰された仏様です。
|
| 平成29年 2月1日 |
|
 般若の面で連想するのは、恨み、妬みに狂った鬼女です。般若は智慧を意味し、仏教では空とならぶ2本の柱ですから、なぜ鬼女の意味を持つのか理解できません。ただ、大般若会のときに、十六善神図を掛けるのですが、この大般若を護る神将は鬼神あり獣面ありで何ともすさまじいのです。また鬼子母神のように、赤ちゃんを喰う悪鬼が、改心して仏法の守りとなる例は多いのだが・・・と探しているうちに 般若の面で連想するのは、恨み、妬みに狂った鬼女です。般若は智慧を意味し、仏教では空とならぶ2本の柱ですから、なぜ鬼女の意味を持つのか理解できません。ただ、大般若会のときに、十六善神図を掛けるのですが、この大般若を護る神将は鬼神あり獣面ありで何ともすさまじいのです。また鬼子母神のように、赤ちゃんを喰う悪鬼が、改心して仏法の守りとなる例は多いのだが・・・と探しているうちに
「外面似菩薩、内心如夜叉」に行き当たり、ハッと思い当りました。私たちが注意しなくてはいけないのは、表はよい顔をして内心は鬼のような人です。しかし、夜叉も鬼子母神のように、悪鬼から仏教の守護者となりました。外面が鬼でも中には慈 悲心をたたえている人を見抜くのが、智慧の力ではないかと思いました。 悲心をたたえている人を見抜くのが、智慧の力ではないかと思いました。
 仏教は否定の宗教だといわれます。煩悩を消して、消し尽くして寂静に至ります。自己を否定し去って、否定しきれない自己を真の自己とします。父母のまた父母を求め続けて仏性に会います。しかし、初期の仏教には肯定をしていく方法もあったのです。それが密教では表に出てきます。「生きるために備わった欲は全てすばらしい」とマイナスのエネルギーを、一気にプラスに転換するすごい考え方です。世間では「英雄色を好む」などと大目に見てきましたが。そのかわり、一歩間違うと味噌も糞も一緒になります。 仏教は否定の宗教だといわれます。煩悩を消して、消し尽くして寂静に至ります。自己を否定し去って、否定しきれない自己を真の自己とします。父母のまた父母を求め続けて仏性に会います。しかし、初期の仏教には肯定をしていく方法もあったのです。それが密教では表に出てきます。「生きるために備わった欲は全てすばらしい」とマイナスのエネルギーを、一気にプラスに転換するすごい考え方です。世間では「英雄色を好む」などと大目に見てきましたが。そのかわり、一歩間違うと味噌も糞も一緒になります。
大乗仏教は自分が悟りを開くという小欲より、人々を悟りに導く大欲を持てといいます。『般若経』の中心に『理趣経』があって、導師が翻転しますが、ここにはあらゆる欲望を最高の歓喜に浄化する秘法が説かれています。薬師如来十二誓願にも本当の喜びを味わわせて、人生の素晴らしさを教える、とあります。援助交際をする娘や、最近の幼児虐待を見ていますと、身も心も捧げた恋をしていないんじゃないかと思います。性も美食も簡単に手に入るようになって、まるごと抱え込んで味わい尽くす貪欲さがなくなったようです。
人生は自分のものです。1歳の赤ちゃんの一生も百歳の長寿も、本人には一生ですから優劣はありません。比較しても無駄なのです。結 局、自分は自分の花を思いっきり咲かせればいいのです。 局、自分は自分の花を思いっきり咲かせればいいのです。
|
| 平成29年 1月1日 |
|