現代の奥様達は、奥になど納まっていないで表に姿を現すばかりか、積極的に外に出るのが当たり前のようになりました。中には外にばかり出ていて、奥様の呼称よりそとさまの方がピッタリと思われる夫人も多くなりました。
では、奥様のことを山の神とも言うのはどうしてでしょうか?いろは歌を思い出してみてください。「うえのおくやまけふこえて・・・」。
そうですね。やまの上にはおくがあります。上と神をひっかけた言葉あそびですが、面白いと思いませんか。もちろん本物の山の神は山を支配する神様で、山の動植物にその影響を与えます。
昔、農家では、この神様が春になると山を降りて田んぼに宿り、秋にはまた山にお帰りになると考えました。今でも田んぼのことをヤマと言ったり、田んぼの神様を山の神様と言ったりすることから、田んぼの神様と山の神様が同一神であることは容易に想像できましょう。春と秋にはおはぎやもちを供えてこの神様を送迎する民間信仰も、今に伝えられています。またこの神様に豊受大神とか大山祇神という具体的なお名前をつけてお祀りする神社がありますが、一般的には社を作らず、単に田の神、山の神として敬っていることが多いようです。いずれにしても山の神は動植物を育む有り難い神様です。
各家庭の山の神=奥様も、子宝を育み、家庭に食事を与える有り難い存在です。山の神のご託宣(口やかましい奥さん)をよく聞いて、豊かな家庭をエンジョイすることにいたしましょう。
日本は昔、文字を持たない国でしたが、仏教とともに伝来した漢字や悉曇(インドの音声語)に基づいて、日本語の発音が文字化され、整理されました。
アイウエオは悉曇五十字門に基づいて日本語の発音を組織的に図式化したものですね。五十音図の最初のものは、11世紀に作られたとされる醍醐寺蔵「孔雀経音義」ですが、江戸時代に契沖というお坊さんが、東密悉曇学の代表作¬=浄厳の「悉曇三密鈔」によって現行の五十音図を作成しました。日本語の音を仮名で5段10行に配列、ア行のイ・エがヤ行に、ウがワ行に重複しているので、つごう五十音となるわけです。以前、ほんの少しだけ梵語(古代インド語)を習った時、アで始まりンで終わる梵語の配列が日本語によく似ているなあと思ったことがありました。実は、日本語の方が梵語を真似て整理されたものだったというわけです。どうりで仁王様のア・ウン像の説明が、インド・日本と別なのにピッタリ合うわけです。
一方、いろはの方はアイウエオの成立時より時代が遡ります。平安時代に弘法大師が、日本の字音に仏教的意味を持たせ、しかも重複することなく並べて歌にしたものと言われています。「色はにほへと散りぬるを、我が世たれそ常ならむ、有為の奥山けふ超えて、浅き夢みし酔ひもせす、ん」というこの歌は「諸行無常 是生滅法 生滅々已 寂滅為楽」という涅槃経に出てくる雪山偈とピッタリ符号します。最近では弘法大師の作ではないとも言われておりますが、いずれにしても仏さまの教えを歌ったものであることは確かです。
日本の言語文化は、まさにインド伝来の仏教文化に負うところが大きいと言えましょう。
大人になるって本当はどういうことなのでしょうか。実は大人は元々仏・菩薩の呼称だったのです。それが敬意を表して長老をもそう呼ぶようになり、徳のある人を誰でもそう呼ぶようになり、だんだん下がって、一人前のものを一般的にそう呼ぶようになりました。だから本来は大人になるって大変なことだったわけです。遺経には、八大人覚といって大人であるための八つの条件が示されております。すなわち、少欲・知足・遠離・精進・不忘念・正定・智慧・不戯論を行ずることがそれですね。また「能く忍を行ずる者は乃ち名づけて有力の大人となす」ともありますから、堪え忍ぶことが文字通りの大人(おとな)しいことなのかもしれません。体だけ大きくなって齢だけとっても、仏道を修めなければおとなにはなれません。
伝教大師最澄様は「大道未だ弘まらず、大人興り難し」といわれました。はやく道を求めて大人になりましょう。また、小人とは大人の反対語で、閑居して不善をなす輩が小人です。いわゆるこどもは子供であって小人という蔑称はあてはめるべきではないと思うのですが・・・・。
こどもの中にも大人が居て、おとなの中にも小人が居ます。
丈夫に大をつけた大丈夫も志村けんの「大丈夫だあ~」で、小さな子供にまですっかりおなじみになってしまいました。 また転んだら誰かが「大丈夫ですか?」と声をかけてくれますが、いったい大丈夫とはなんなのでしょう。
如来十号に調御丈夫というのがありますが、これは私たち人間を調えてくれる者という意味を持つ如来の尊号です。また、丈夫拝といえば全身を使う五体投地の礼拝のことで、男子のする礼拝の仕方、といわれました。これは坐ったままでする女人拝と対になっていました。丈夫の下の文字だけをとれば夫という字で、男性をさす言葉だということがわかります。こうしてみると、丈夫とは人間のこと、特に男性をさす言葉だったようです。女性にして丈夫なら女丈夫というそうですが、とにかく人間で、男性で、男性の中の男性であれば、強いもの頼れるものでもあるわけで、「正道を実践して退転しない者」の意から転じても不思議ではありません。「德山もし丈夫なりせば婆子を勘破する力あらまし」という文に見られる丈夫とは、この実践修行者のことであり、「観音大士は大丈夫なり」などという時の丈夫は、救済を実践する力強い菩薩ということです。
このように色々な使い方をされる丈夫ですが、要するに、男の中の男であり、人間の中の人間であり、人間をリードして力強く仏道を進む者こそ真の大丈夫ということでしょう。私たちも仏さまの調御をあおぎ、煩悩具足の我もまた大丈夫ならんと修行させていただくことに致しましょう。あなたは大丈夫・・・?
 「ご馳走さま」というと、いまでは食事のときの言葉と思われておりますが、その文字を考えると、どうしてそんな言葉になったのか不思議に思いませんか。
「ご馳走さま」というと、いまでは食事のときの言葉と思われておりますが、その文字を考えると、どうしてそんな言葉になったのか不思議に思いませんか。馳走とは馬車を疾くかけ走らせるとか、年月が走るように過ぎ去るといういみです。古文書に出てくる馳走は、だいたいそのような意味で使われています。これが、人をもてなす意味に用いられるようになったのは、日本だけの、それもかなり時代が下がってからのことらしいのです。
 もちろん、食事を用意するためには材料を求めたり煮炊きをしてかけまわることから、食事などのもてなしをする意味に変化したのでしょうが、その意味に変化させる日本人の心を考えてみましょう。お坊さんは食事の時おとなえごとをしますが、その五観の偈の第一に「功の多少を計り、彼の来処を量る」という文句があります。これは「多くのおかげを思い、感謝していただきます」と現代風に言いかえられていますが、この心が「ご馳走さま」の心ですね。
もちろん、食事を用意するためには材料を求めたり煮炊きをしてかけまわることから、食事などのもてなしをする意味に変化したのでしょうが、その意味に変化させる日本人の心を考えてみましょう。お坊さんは食事の時おとなえごとをしますが、その五観の偈の第一に「功の多少を計り、彼の来処を量る」という文句があります。これは「多くのおかげを思い、感謝していただきます」と現代風に言いかえられていますが、この心が「ご馳走さま」の心ですね。ご馳走さまだけではなく、お世話さま、ご苦労さまなど、日常よく耳にする挨拶言葉はその多くが、相手の立場に立ってその労をねぎらい感謝する言葉です。日本人の美しい言葉としては、まず「ありがとう」が第一にあげられるそうですが、これらもありがとうにおとらず美しい言葉と言えるでしょう。
自分が多くのおかげをいただき、生かされている。だからそれらに感謝せずにいられない。こういう日本人の生き方を大切にしたいものですね。感謝の言葉にはきっと美しい花が咲いてゆくことでしょう。
 法華経薬王品に「我が滅度の後の所有の舎利、亦汝に付属す。正に流布せしめ、広く供養を設くべし」という句がありますが、この句からわかるように、流布とは本来、世間に広く伝えることであり、仏の教えが遠くまで流れ広まることをいいました。流布が今でもルフという仏教読み(呉音)で使われていることをみれば、これが仏教語であることを納得していただけるでしょう。
法華経薬王品に「我が滅度の後の所有の舎利、亦汝に付属す。正に流布せしめ、広く供養を設くべし」という句がありますが、この句からわかるように、流布とは本来、世間に広く伝えることであり、仏の教えが遠くまで流れ広まることをいいました。流布が今でもルフという仏教読み(呉音)で使われていることをみれば、これが仏教語であることを納得していただけるでしょう。一方、流通はルズウという仏教読みを離れて、リュウツウという漢音で一般に親しまれるようになりました。流布も流通もほぼ同じ意味ですが、「経典を広く伝えるため、弟子にこれを与える旨を表す経典部分」は、流通分といわれております。今日、流通といえば経済用語であってこれが仏教語などとは思いもよらない人が多いのですが、流通物とは本来、世の中に広め伝えるべき仏教のことであり、流布、流通すべきものの元祖は仏教に他ならぬことを知っておきたいものです。
次に、渡りに船という句ですが、これも薬王品にある句が一般に広まったものです。薬王品には法華経が大いにみんなのためになるということを、色々なものに喩えている部分がありますが、その一節に「・・・・子の母を得たるが如く、渡りに船を得たるが如く、病に医を得たるが如く・・・・」というのがあるんですね。人生の荒波に揉まれてアップアップしている私たちですが、波間に流布、流通するものをよく見定めて、仏教という渡し船に出会ったらいち早くこれに乗って、悟りの岸に向かうことができれば幸だと思うのです。また、仏教者は、人々が仏法に接することのできる機会を多くして、人々がいつでもこの渡し船に乗れるよう配慮すべきであると思うのです。これが本当の「渡し船」なのですから・・・。
障礙の意味はもちろん精神的なもので、さとりを得るために除かなければならない障りや礙げとなるものをいいました。この障礙には四種類ありまして、
①仏法をそしること、②自己に執着すること、③苦しみを恐れること、④生きとし生けるもののためになろうとする心がけが無いこと、が数えられます。この四つが基本的な障礙ですが、いまの国語では拡大解釈されてハードルやハンディキャップまで障害に加えられ、読み方が変えられた上、字も礙から害に変えられてしまったようです。
仏教でいう障害はあくまでも心の問題であり、私たちの心にたまる塵芥をさす語です。心は本来清らかで明るいものなのですが、この塵芥が障害となって自由を失うばかりか、暗く悩める姿となってしまっているといえるでしょう。この心の本来の姿を取り戻せるのは私たちめいめいでしかありません。自分の心を救えるのは自分しかないということです。ちょうどお腹が空いているときに、他人にご飯を食べてもらっても自分のお腹は減ったままのように、他人に勉強してもらっても自分の知識は増えないように、他人に修行してもらっても自分の心は救われないままです。自分が食べ、自分が勉強してこそ、自分の体が出来、自分が賢くなるように、自ら自分の心をきれいにするのでなければなりません。
よく自分の悩みを他人のせいにする人がいますが、それでは一生悩んだまま救われることなどないでしょう。自分の障害は自分で取り除いてゆきたいものです。
ところで、今ここに取り上げたいのは、もう一つ想起される「尼」についてです。尼という文字は、「人に近づきならぶ意」であり、釈迦牟尼・陀羅尼など仏教語の音写用文字に使われました。尼に「女性」の意味が付加されたのは、ビクシュニの音写語として比丘尼と書かれてからでしょうか。また尼を<あま>と訓ずるのは、梵語で母を表す阿摩(アンバー)に由来します。和訓だと思ったあまがインド語だったというわけですね。
仏教教団の始めの頃お釈迦様は、女性が及ぼす出家者への感覚的魅力を警戒し、女性の出家を許可しませんでした。しかしその後、お釈迦様の育ての母・摩訶波闍波提(マハーパジャティ)の熱心な懇願に応じ、遂に女性の出家を許さざるをえなくなったそうです。このお方が仏教教団最初の比丘尼ですね。また、日本での最初の比丘尼は、敏達天皇13年に高麗の帰化僧・慧便について得度なされたという善信尼(鞍部主司馬達等の娘)です。
今では一般に、出家して僧籍に入った女性を比丘尼と言い、これを省略して尼とか尼僧さんと言っていますね。尼は本来尊称として使われてきたのですが、これを「あま」と訓じ、時には罵りの語として一般女性につかわれるようになったことは、残念というほかありません
そのせいか尼僧自身が尼を付けて呼ばれることを嫌がるようになり、最近は名前を拝見しただけでは、男僧か尼僧かわからない時代となりました。
尼がどうして尊称でなくなったかはともかく、最初は尼<母の意>が、文字通りお釈迦さまのお養母様だったことを覚えておいてほしいものです。
辞書で聖域を引きますと、①戦火などを及ぼしてはならない地域 ②問題として取り上げてはならない事柄 等と出てきます。その程度の解釈なら、前のような発言が出てくるのは当然かもしれません。
本来の聖域とはもちろん、清浄で尊い境地、言語でいうニルヴァーナ(さとり)の世界を指す語です。この世界は、凡人が入り込むすきまのない地域であり、凡人が如何ともしがたい聖そのものしかありません。
仏教教団は、この聖域(仏教読みではショウイキ)にあこがれ、聖域に住む人ブッダになることを目標とする人々の集まりと言えるでしょう。聖域に住む人を聖人(ショウニン)とも呼んでいますが、この聖人も時代とともに使い方が変化してきたようです。仏教内部でも、上人より更に尊い人ということで、宗祖などを聖人(親鸞聖人等)と尊称しています。
おそれおおいことですが、お釈迦さまのように、ブッダの列に加わらんと修行するのが仏教徒であり、史上、聖域に達した方々もおられるということです。
また、この聖人達の残された書物を聖典といいます。経典と言えばいわゆるお経のみを指しますが、聖典とは経・律・論の三蔵全体を指す言葉といえましょう。私たちは仏教聖典によって精進する必要があるのです。
とにかく、聖とは仏さまとお悟りに関する語でした。他の宗教や政治家がこれを借用するのはかまいませんが、聖域にあらざる聖域があったり、聖典にあらざる聖典があったり、はては聖人を名乗るペテン師が出たりすることのないよう、願いたいとおもいます。
 今は「相手の言動をおさえとどめる」などの意味に用いられている制止ですが、本当に制止しなければならないのは何でしょうか? 仏教事典には「欲望を制し止めること、戒の異名なり」と出ておりました。欲望を制止することは、自分本来の姿のたちかえることであり、そのためには戒を保つことが一番です。制止の状態とは右にも左にも傾かず、前にもかがまず、後ろにもそり返らず、中道実相と一体になることであり、坐禅の姿に一致します。
今は「相手の言動をおさえとどめる」などの意味に用いられている制止ですが、本当に制止しなければならないのは何でしょうか? 仏教事典には「欲望を制し止めること、戒の異名なり」と出ておりました。欲望を制止することは、自分本来の姿のたちかえることであり、そのためには戒を保つことが一番です。制止の状態とは右にも左にも傾かず、前にもかがまず、後ろにもそり返らず、中道実相と一体になることであり、坐禅の姿に一致します。制止も戒も中道も同じことだと言われても解りずらいでしょうが、同じことを違う角度からとらえたと考えたらどうでしょう。
本来の制止をすれば解るかもしれません。
次に停止とは一般的には、呼吸が停止するとか、車を停止線に止めるとか使われていますが、これも本当に停止(仏教読みはチョウジ)しなければならないのは私達の邪心に他なりません。仏教では五停心観と言いまして、邪心を停止する五種類の観法があります。つまり、①外界が不浄だと観じて、貪りの心を停止する不浄観 ②相手の立場に立って瞋りの心を停止する慈悲観 ③物事の道理をよくみて愚痴の心を停止する因縁観 ④広い世界をよくみて我見を停止する界分別観 ⑤呼吸を整えて散乱の心を停止する数息観です。貪、瞋、痴、我見、散乱という五つの心の過ちを停止して得られる仏道修行の成果を五停心位と言います。
私達凡人は、わかっていてもなかなか本当の制止や停止ができません。自動車を制止したり停止したりすることは結構得意なんですが、自分の心にブレーキ操作することは難しいですね。運転手が事故を起こさないためには、アクセルよりブレーキ操作に注意するように、人生に事故を起こさないためには、心の中の煩悩というアクセルよりも、戒というブレーキに意を注ぐことが大切ではないでしょうか。
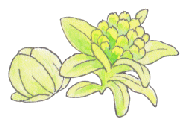 人間が他の動物と違うことのひとつに「手を使う」ことがあげられますね。人間は4本足のうち前の2本を手に進化させて、いろんなことをしてまいりました。2本の手は大変役立ってきましたが、2本ではとても足りないお方もいらっしゃいました。たくさんあれば、あの手この手を使って何でもできる、いよいよとなったら奥の手もある。
人間が他の動物と違うことのひとつに「手を使う」ことがあげられますね。人間は4本足のうち前の2本を手に進化させて、いろんなことをしてまいりました。2本の手は大変役立ってきましたが、2本ではとても足りないお方もいらっしゃいました。たくさんあれば、あの手この手を使って何でもできる、いよいよとなったら奥の手もある。手が2本しかない人間社会で「あの手この手」というと、いろいろな手段方法を指し、「奥の手」はとっておきの手段方法を指しますが、あの手この手という発想の元祖は千手観音様でしょう。
千手観音様は六観音のおひと方で、限りない慈悲を表す菩薩様です。あまたの衆生をあわれんで救いとらんとするためには、2本の手ではとてもたりません。そこで我が手を千本に増やし、文字通りあの手この手奥の手で私たちを助けてくださいます。梁塵秘抄に「万の仏の願よりも千手の誓いぞ頼もしき」とあるとおりでしょう。千の慈悲の手をそなえて、生あるものをどの手で救おうかと工夫なさっておられるのですね。
また、千手観音様はインドのシヴァ神に比肩する実力者で、日本では奈良時代から信仰されている延命・滅罪・除病の観音様です。そのお姿は、四十二臂・二十七面で表されているのが普通ですので、千手と言っても、広大無辺を千という数で表現したのだと考えるのがよいでしょう。唐招提寺金堂の千手観音像は、実際に千の手を持っておられるそうですが・・・
千の眼をもって常に私たちを見守り、千の手で油断なく救いとってくださるなんて、有り難いではありませんか。私は、プール監視をこの観音様に頼んだら最高だろうなどと、失礼なことを考えてしまいましたが、微力な人間である私たちにもできることは、せめて精神だけでもこの観音様に倣うことでしょう。そして、この2本の手を有効に生かし、世のため人のために使いたいと念じてやまない次第です。
 「せっかく良い縁がきたのに本尊様がさっぱりだ」などと言えば、あることの中心人物とか当人をさすこともある本尊ですが、もちろん本来は人間をさす言葉ではありませんね。礼拝の対象として寺院に祀られるもっとも主要な仏さまのことで、数ある仏像中、真ん中に祀られているので中尊といわれることもあります。そしてお寺で何が一番大切かと言えば、この本尊様に他なりません。また何様を本尊様とするか定められている宗旨もありますが、おおかたの寺院ではその縁起によって本尊様が定まっているようです。いずれにしても、本尊様ほど大切なものはないのですが、今日のお寺詣りの様子をみると、そのお寺の本尊様のことなど知らないままにお参りしている人が多いようです。
「せっかく良い縁がきたのに本尊様がさっぱりだ」などと言えば、あることの中心人物とか当人をさすこともある本尊ですが、もちろん本来は人間をさす言葉ではありませんね。礼拝の対象として寺院に祀られるもっとも主要な仏さまのことで、数ある仏像中、真ん中に祀られているので中尊といわれることもあります。そしてお寺で何が一番大切かと言えば、この本尊様に他なりません。また何様を本尊様とするか定められている宗旨もありますが、おおかたの寺院ではその縁起によって本尊様が定まっているようです。いずれにしても、本尊様ほど大切なものはないのですが、今日のお寺詣りの様子をみると、そのお寺の本尊様のことなど知らないままにお参りしている人が多いようです。初詣や観光などはこの最たるものと言えましょう。できれば、そのお寺の本尊様がどんな仏様なのかくらいは知っておいてほしいものです。本尊様次第ではお参りしないなんてことになっては角がたちますが・・・
もっとも、何様が祀られているか無関心という点では仏教より神道の方がひどく、たとえば神前結婚で、なんという神様の前で挙式したのかチャンと言える人などほとんどいないと言ってよいでしょう。日本人の信仰形態としては本尊様など何様でもよく、有り難そうな雰囲気が大事というむきもありますね。考えようによっては、この方がみんなと仲良くするために望ましい形なのかもしれません。外人には奇異に思われるでしょうが、本尊様が何様であろうと、人が大切に思うものは自分にも同じとして、いろんな神様や仏様を拝んだり、信仰の違う相手の宗教行事におくめもなく出席し、その儀式に平気で参加する_こんなあり方が暮らしの中から生まれた智恵であり、日本宗教が世界に誇る長所なのかもしれません。