|
「愛宕神社」の虚実 昭和初期にかごめ歌を採譜した山中直治という作曲家は千葉県野田市の出身です。その野田市の愛宕神社には、群馬県花輪出身の二代目・石原常八(石原三郎主信)という彫刻師の手で文政七年(西暦1824年)に造られた「籠の中の鳥(鶏)」の彫刻があります。 この愛宕神社の創建は平安時代・延長元年(西暦923年)であり、江戸時代・文政七年十月二十四日(西暦1824年12月14日)に、関東各地の寺社を手掛けた埼玉県川俣村(羽生市)の大工の棟梁・三邑(三村)正利と野田の大工の棟梁・荒川正行によって11年の歳月を掛けて再建されたそうです。 なお、西暦1991年10月4日と10月11日に日本テレビ系列で放映された「TVムック・謎学の旅」というテレビ番組の、最後の「かごめの回」の前半(10月4日分)の中では、同神社の禰宜を務めた人の話として「彫刻は再建以前のものと同じ」という説が紹介されています。 愛宕神社といえば、明智光秀が本能寺の変の直前に里村紹巴(連歌師)らとともに京都・愛宕山の愛宕神社で連歌会・愛宕百韻を行ったことが有名です。 --- 1998年のGWに東京都港区の愛宕山にお参りをしました。 由緒によると、祭神が火産霊命(火の神)、罔像女命(水の神)、大山祗命(国土の神)、日本武尊(武の神)で、脇殿に勝軍地蔵菩薩(徳川家康公御持仏)、太郎坊本地仏(修験道祖神)、普賢大菩薩(辰年巳年守本尊)、末社に太郎坊社(猿田彦命)、福寿稲荷社(倉稲魂命)、弁天社(市杵嶋姫命)などがあります。 猿田彦は日本の土着の神(国津神:くにつかみ)の代表です。なぜ、太郎坊社の神が猿田彦であるのか不思議に思ったのですが、「修験道祖神」を「修験の道祖神」と読み替えます。「猿田彦」は「道祖神」と同一視されるのだそうです。 --- 「おでっせいあ」というブログを運営されていた方が撮影された野田の愛宕神社の彫刻群の写真をもとに、「雄峯閣 ―書と装飾彫刻のみかた―」というサイトを運営されている方が、その図像の意味を読み解いていらっしゃいます。それによると、野田の愛宕神社の彫刻群は、鎌倉時代末期に成立した石清水八幡宮の霊験記である『八幡愚童訓』をもとにして造られているのだそうです。 野田の愛宕神社にある彫刻群については、「江戸彫工系譜」というサイトにあった[石原流]の項目や、「ハニーちゃんがゆく!」の当該ページのブログも参考にしました。 --- 2010年の4月に野田の愛宕神社にお参りをしました。 右側面は、左から「天宇受売命の舞」「岩戸を開ける天手力男命」です。同神社にある解説板を参考にしました。 背面は、左から順に「娑竭羅竜王」「竜宮で琴を奏でる竜女」「神功皇后の新羅出兵」です。同神社にある解説板、『寺社縁起(日本思想大系20)』所収の『八幡愚童訓 甲』を参考にしました。 左側面は、左から「草薙剣を持つヤマトタケル」「逃げる熊襲」です。同神社にある解説板を参考にしました。 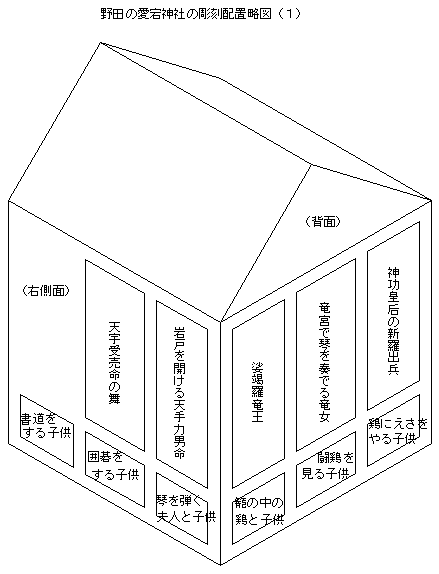 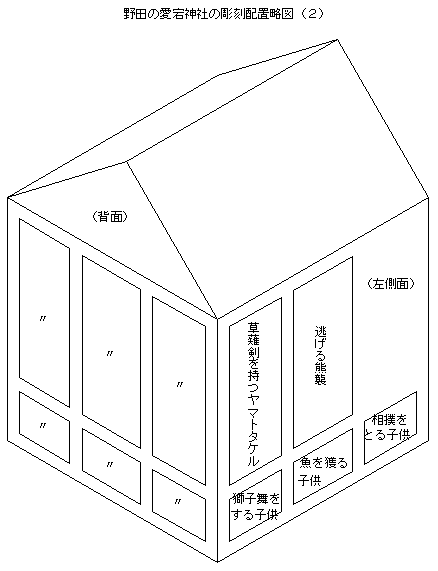 --- なぜ野田の愛宕神社に石清水八幡宮の霊験が描かれているのかについて考えてみます。野田の愛宕神社の裏手には、かつての神仏習合の名残である「勝軍地蔵尊」のお堂があります。すなわち、愛宕神社と石清水八幡宮のどちらにも「軍神」が祭られているという共通点があります。 また、東京都港区の愛宕神社では、猿田彦とのつながりを知ることもできました。そして、野田の愛宕神社にある八幡愚童訓の彫刻には、神功皇后の新羅出兵の際に安曇磯良を呼び出した神楽のたとえとして、天照大神を天の岩屋戸の外へと導く神楽を舞った天宇受売命とその夫の猿田彦の姿が描かれています。 ここで、戦国時代における、猿田彦の意味付けを推測すると、「秀吉」=「猿」という図式が思い浮かびます。 この彫刻群は、神功皇后の新羅出兵に、豊臣秀吉の朝鮮出兵をなぞらえている、と考えることもできます。 そもそも野田の愛宕神社の彫刻と記紀神話とを比較すると、「猿田彦」はその場に居るはずのない存在です。うがった見方をすると、「猿田彦が不要」すなわち「秀吉の朝鮮出兵が不要」という意味が込められているのかもしれません。 反対の側面に描かれているヤマトタケルについて考えてみます。豊臣秀吉を猿田彦にたとえていることと同様に、何かをヤマトタケルにたとえているという推測が成り立ちます。記紀において「ヤマトタケル」についての記述は、神功皇后の新羅出兵の「前の時代」にあたります。そこで、秀吉の朝鮮出兵の「前の出来事」である本能寺の変を起こした「明智光秀」がそれに対応すると解釈します。 『八幡愚童訓』には、神功皇后の新羅出兵の際に、朝鮮側の兵の多さに対して日本側の兵が少な過ぎることが述べられ、朝鮮側が「鶴翼の囲」「魚鱗の陣」を構えているのに対し、日本側の戦いの分が悪いことを「籠に入る鳥」「網にかかる魚」にたとえています。一方、野田の愛宕神社の彫刻は、背面下段左に「籠の中の鳥」、左側面下段中央に「魚を獲る子供」が描かれています。これは、神功皇后の戦いの分が悪いことを示すと同時に、明智光秀の戦いの分が悪いことを表しているとも解釈できます。 神功皇后はその後、竜宮で得た「干珠・満珠」の力を使って海の水を操り、逆転勝利を収めます。野田の愛宕神社にも同様に、神功皇后に捧げられる「二つの珠」が描かれています。一方、秀吉については、光秀を破ったあと、九州征伐をした、という意味を表していると解釈できます。 野田の愛宕神社の彫刻群全体としての意味を総括すると、記紀神話と八幡愚童訓という説話をもとに、明智光秀が秀吉に敗れ去ったことと、秀吉の九州征伐を表している、と読み解くことができます。 --- <参考図書> ・ 江戸彫工系譜 http://edobori.fan-site.net/ (2019年12月現在 ウェブサイト終了) ・ おでっせいあ http://blogs.yahoo.co.jp/dnnyh656/ (ヤフーブログは2019年12月15日に終了) ・ 雄峯閣 ―書と装飾彫刻のみかた― https://www.syo-kazari.net/ ・ ハニーちゃんがゆく! https://ameblo.jp/tweet-tweeties/ ・ 寺社縁起 日本思想大系20 校注者:桜井徳太郎・萩原龍夫・宮田登 岩波書店 1975年 ・ 群書類従 第一輯 神祇部 訂正三版 編纂者:塙保己一 続群書類従完成会 1992年 ・ 古事記(上) 全訳注 著者:次田真幸 講談社 1977年 ・ 古事記(中) 全訳注 著者:次田真幸 講談社 1980年 ・ 日本書紀(上) 全現代語訳 著者:宇治谷孟 講談社 1988年 ・ 毎日新聞 大阪 テレビ番組表 1991年 --- かごめかごめ ずいずいずっころばし あんたがたどこさ とおりゃんせ はないちもんめ 戻る |