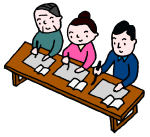「住職の独り言」・・・・その36 「住職の独り言」・・・・その36
お寒くなりました。
晩秋の頃は、暖かな日が続き今年の冬は暖冬かな… と思っておりましたが、師走に入ったら、連日平年の気温を下回る日が続き、このままでは先が思いやられます。
今年も残り僅かとなり、なんとなく気ぜわしくなってきました。まさに師が走りまわるようにな時期になりましたが、皆様いかがお過ごしですか。風邪などひいていませんか。忙しさの中でも、心静かに今年を振り返り、自分自身を振り返ってみる時間を作ってください。現代人にはこのような時間がまったく無いと言ってもいいかもしれません。それが、最近の不幸な社会現象を生み出している、原因の一つにもなっているのではないでしょうか。老若男女、大人から子供までがもっと自分をじっくりと見つめ、心静かに過ごす時間が必要であると思います。
さて、当山では今年の春から、月に一度、「座禅の会」と「写経の会」を開催しております。小生もまだなれませんし、宣伝が足らないのか、毎回参加人数は少ないのですが、お盆の8月を除き休まず行っております。
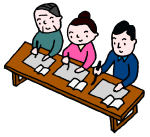 聞くところによりますと、今、写経が静かな隠れたブームにもなっているそうです。なぜ、今、写経が現代人の心をとらえるのでしょうか。 聞くところによりますと、今、写経が静かな隠れたブームにもなっているそうです。なぜ、今、写経が現代人の心をとらえるのでしょうか。
今、社会のそこここより、人間復興、人間性の回復という叫び声が上がり、そのために精神文化の心の世界が見直されてきました。
科学万能と盲信してきた物質文明、IT社会の弊害によってゆきづまった現代人が、もう一度根本から人間としての行きかたを考え直してきたからではないでしょうか。
人間本来の心と姿を求めていろいろの修養の道がありますが、写経はその一つとして、老若男女を問わず強く人々の心をとらえてその共感が広がり高まっているようです。事実、写経を行っている人々が大きな安らぎをえられ計り知れない功徳が実証されているからです。
では、写経とはなんなのか、その精神と意義、作法と実修の姿などをのべながら、その本来の目的と功徳についてこれを尋ねてみましょう。
※ 写経の本来の目的とその意義
写経とは「お経を写す」と書きます。お経とは申すまでもなく仏さまの説かれた教えで「この宇宙と生命と人間」の正しい姿と、あり方を示した真理で、仏の心そのものでもあります。
人々は、この尊い経典を永遠の真理として大切にこれをあがめ、「受持し、読誦し、書写し、解説」して、その心を守り、伝え、広めてきました。ですから写すことは「移す」ことで、仏の広大な智慧と慈悲の心とその教えを、私たちのこの身この心に正しく移し導入しようとした修行の姿を「写経の行」といったのです。
経典の中に、「心と、仏と、衆生」と、差別あることなしと示されています。人間本来の心と、仏の心、仏の教えは同じという教えですから、一心に仏を念じて写経の行に励むならば、必ず仏の大慈悲が、私たちのこの身この心にゆり動いてきて「文房四宝」といわれる、筆墨紙硯などを縁としてその作法の中から写経の功徳が自然に現れてきて、真実の自分の発見となるのです。
※ 写経の精神とその作法そして莫大な功徳
本来の写経の作法は、「如法写経」といってきわめて厳粛なものですが、私たちが日常生活の中でこれを行うには、なによりも、その決意と心を「我が身ながらの師」としてたいせつにし「心の写経」を行ってください。
天台宗では、比叡山に伝わっている、宗祖伝教大師の「教師観行」や、慈覚大師以来の如法写経作法などの厳格な方法を基にして、写経のお手本である「法華経、般若心経、観音経」などの経典に盛りこまれた仏の教えをわかりやすく解説して、その手順、作法と、心がけ、納経の功徳などを書いた「写経のすすめ」という小冊子を用意してそのご指導に当たっております。
お経は、ただその文字を見るだけで、受持するだけでも莫大な功徳があるといわれています。まして、これを読誦して書写するのですから、更にその功徳は大きく広がって自分だけでなく、過去のなき人々にも、現在の人々にも及び、自他共々にめざめた人間として、日々感謝と喜びの生活を送ることができるのです。
その昔、仏がヒマラヤの山中で永遠の真理を求めて難行苦行を積まれておられたときに、どこからともなく心の耳に妙なる経文の一節が聞こえてきました。
諸行は無常なり(いろはにおへど散りぬるを、わが世誰れそ常ならむ)…そして、その後半の悟りといわれる、寂滅為楽の偈(有為の奥山けふ越えて、浅き夢みし酔もせす)を、うるために、悪鬼の求めに応じてその身をささげてこれを求められ、その悟りの偈をかたわらの石に刻んで後世の人々のためにのこして下されたという物語があります。これが写経のはじめであり、又、その精神ともいわれています。
「梵網菩薩戒経」には「皮を剥いで紙となし、血を刺して墨となし、髄を持って水となし、骨を折いて筆となし、仏の教えを書写すべし」と、この壮絶なる仏の決意と、法を伝える仏道修行の厳しさを伝えています。厳正な写経を行うことは至難ですが、この心を忘れずに現代作法でけっこうです、明日からと言わずお始め下さい。写経行はその人に新しい人生の門を開いてくれます。
今年も、一年間お付き合い頂きありがとうございました。
毎回、オシャベリの題材となる資料を探しながら、つくづくと我が身の不勉強を感じております。
こんなことでは、お忙しい時間を割いて読んで(聞いて)くださる皆様に誠に申し訳ないと思いつつも、一向に進歩しておりません。
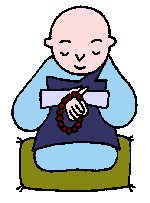 こんな愚僧ですが、これからもお付き合いの程よろしくお願い申し上げます。 こんな愚僧ですが、これからもお付き合いの程よろしくお願い申し上げます。
当山HPに、ご意見ご希望がございましたら、ご遠慮なく掲示板にてお聞かせください。皆様からの反応が良き糧となります。
それでは、皆様くれぐれも御身体ご自愛頂き、良きお年をお迎えくださいますようお祈り申し上げます。
|
 「住職の独り言」・・・・その36
「住職の独り言」・・・・その36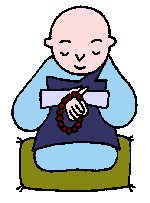 こんな愚僧ですが、これからもお付き合いの程よろしくお願い申し上げます。
こんな愚僧ですが、これからもお付き合いの程よろしくお願い申し上げます。