畜生とは 「愚鈍で世の人に養われるもの」という意味で、牛・馬・鳥・魚などを指します。
家畜といえば、家で飼っている畜生ということになりましょうか。
日常会話の中で使われる畜生は、あまり良い意味では使われません。あん畜生、こん畜生、畜生め等と、相手を侮辱する時に用いられるようですが、実際お経の中でも六道のうち人間より下、それも下から三番目の世界に住むものをさします。
一番下の地獄、下から二番目の餓鬼、それにこの畜生界までを三悪道といい、そこは悪人が死後罪の報いで落ちる世界とされています。
それに対して、六道のうち上の三つ、修羅、人間、天上を三善道と称しています。
輪廻転生という見方をもって私たちの世界を見ると、人間に限らずあらゆる生物は寿命の長い短いの差こそあれ、いずれ死に、そして生まれ変わることをくりかえしております。
私たちはいま、人間界に生まれてきておりますが、次の世は一体何に生まれることになるのでしょうか。地獄へは行きたくないし、餓鬼や畜生にも生まれたくありませんね。その ためには良いことを積み重ねて一生を過ごしておかなければなりません。 ためには良いことを積み重ねて一生を過ごしておかなければなりません。
その貯金高によっては、もう一遍人間に生まれるなんてケチなことを言わず、天に生まれて楽を受け、十方の浄土へ行くのも心のままになるとか、仏さまとなって不退転位につくとかできるでしょう。また心がけ次第では、こうして生きてこの世にあるうちに極楽を感じながら暮らせると思います。 |
|
今では珍しくなりましたが、子だくさんの夫婦にとって、子育て時はまさに苦労の連続であり、奮闘記でも書けそうな毎日を過ごしているわけですが、子供が一人また一人と巣立って夫婦二人きりになると、かえって現在が不幸であるかのような気持ちにおそわれます。そんな時「あの頃はあの頃でよかったし、今は今で二人っきりも幸せだ」と思えれば最高なのですが…。
私達は凡人ですから、ついつい過去を愚痴り、現在の生活を物足りなく思いながら日々を送ってしまいます。
「日々是好日」、この句はそんな私達を励ましてくれるよい句だとは思いませんか。日々毎日のことでヒビともニチニチとも読まれ、好日はきちじつ吉日のことでコウジツともコウニチとも読まれていますね。日本人はこの句を掛物や横額に書いて部屋などに飾り、日常に慣れ親しんでいますが、出典は中国の書<へき碧がん巌ろく録>です。作者はうんもん雲門ぶんえん文偃という十世紀はじめの禅僧で、雲門山で三十年ほど住職されました。「仏教を信ずる者は、いたずらに過去を悔いることや、未来に望を託すことだけに時を費やさず、常に今日を生き生きと生きぬくことに心しなければならない。毎日毎日が全部よい日なんだよ」と文偃禅師はさとされているのです。「今日は日が悪い、今日はしょうがない」などと言っていると、良い日など無くなってしまうでしょう。一日一日がかけがえのない一日であり、今日の一日をシッカリ過ごすことが正しい 仏教者の生き方であるとのすいご垂語と位置づけることができましょう。 仏教者の生き方であるとのすいご垂語と位置づけることができましょう。
私達の一生は一年一年の積み重ねですが、その一年は一日一日の積み重ねに他なりません。朝、目が覚めたら「今日も一日命があったか、有り難い、さて今日は何をしようか」と人生修行に精進してみてください。各人各様に必ずできること、すべきことがあるはずです。一日終わった時に、「今日やったこと」を記録できるような日々を送りたいものです。 |
|
「お前と俺は一蓮托生だ」などと使い、行動や運命を共にする同志という意味ですね。現今では、善きにつけ悪しきにつけ、グループをなして物事を共同でやることを指しているようですが、本当の一蓮托生の意味を考えてみましょう。
一蓮の蓮は蓮華です。蓮華はインドの華の王様であり、仏教では仏さまが座られるところを蓮華座といたします。蓮華は泥の中にいて泥に染ま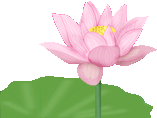 らず、泥の中にしっかり根をはって、すばらしくもまた美しい花を咲かせますから、仏さまを象徴するのにはピッタリなのです。仏さまがすべて蓮の台、蓮台にのっておられるとすれば、私たちが死んで成仏すればやはり蓮台の乗れるはずですね。そうゆうことからでありましょう。仏さまの台座を蓮華に彫刻しておくばかりでなく、お位牌の台座にも蓮華をかたどっているわけです。 らず、泥の中にしっかり根をはって、すばらしくもまた美しい花を咲かせますから、仏さまを象徴するのにはピッタリなのです。仏さまがすべて蓮の台、蓮台にのっておられるとすれば、私たちが死んで成仏すればやはり蓮台の乗れるはずですね。そうゆうことからでありましょう。仏さまの台座を蓮華に彫刻しておくばかりでなく、お位牌の台座にも蓮華をかたどっているわけです。
それにしても本当に死んだら蓮華の台にのれるのでしょうか。一蓮托生とは「あなたも私も死んだら同じ蓮華の上で生まれるのだ」という意味です。蓮華は極楽浄土の池にあるとされますから、死んだら共に極楽へ行く身だということになるのです。
いくら運命を共にする同志だといっても極楽に行くのでなければ一蓮托生とは言えないのです。地獄に蓮は無いそうですよ。人が死ぬと「蓮は上品の花を開き、仏は一生の記を授く」と念じますが、本当に極楽の蓮華台上に生まれることができるよう、善いことを重ねながらこの世を過ごしておきましょう。蓮は仏の象徴で吉祥の花です。娑婆の泥水につかっていても、そこへしっかり根を張って、心は高く上品の花を開いていたいものです。 |
|
愛敬をアイキョウと読む時とアイギョウと読む時の使い分けを説明している辞典がありましたが、皆さまはどう思われますか。また、愛敬を愛嬌と書いたところで、はっきりとした文字による区別があるとも思えません。愛敬とは本来、仏・菩薩の柔和で慈しみをたたえた容貌を表す言葉で、古くはアイギョウと発音されていましたが、いつかアイキョウとも読まれるようになりました。また、敬に代わって嬌の字が書かれるようになったのは、「男は度胸、女は愛キョウ、坊主はお経」ということわざで、女のアイキョウだから女偏だと早とちりした人によって変えられてしまったものでしょう。
次に愛語とは、布施・愛語・利行・同時という菩薩の四摂法の一つで、道元禅師はこう説いておられます。「愛語というは衆生を見るにまず慈愛の心を起こし顧愛の言語を施すなり、慈念衆生猶如赤子の懐いを貯えて言語するは愛語なり」と。つまり、慈愛に裏づけられた愛の言葉――自分のことは一切考えに入れないで、ただ相手のことだけを思いやる、そんな言葉が愛語だというのですね。愛語は面と向かって聞けば心が楽しくなりますし、間接的に伝え聞けば肝に銘じ魂に銘ずるものを感じます。
 |
| 文中の写真は12月末の境内 |
ところで皆さんは「和顔愛語」と書かれた色紙や掛物をご覧になったことがあるでしょう。これは大無量寿経に見える成句で、仏の愛敬の相、すなわち和顔と、この愛語を熟語としたものですね。やわらいだ笑顔をして情のこもったおだやかな言葉をかわす。和顔愛語は法蔵菩薩のお徳を称えた語ではありますが、私たちもかくありたいと願い、是非今年一年といわずこれからずっとこのような姿勢をもって人と接したいものです。 |
|